
2024.04.13 - 城跡・史跡訪問記 其の四
2023.12.02 - 城跡・史跡訪問記 其の四
甲賀流忍術屋敷は、滋賀県甲賀市甲南町にある、江戸時代の屋敷である。外観は古い旧家にしか見えないが、内部には様々な仕掛けが施された正真正銘の忍術屋敷である。元禄年間(1688~1704年)、甲賀五三家(甲賀の地侍)の筆頭格であった望月氏本家の邸宅として築かれた。屋敷内には、甲賀流忍術の奥義を記した古文書や、手裏剣、まきびし、忍者刀などの武器などが展示されていて、忍者が確かに実在していたということを感じさせてくれる。

↑望月氏旧邸

↑落とし穴

↑どんでん返し

↑二階見張り窓











↑隠し梯子



↑見張り窓

↑縄梯子

↑三階


↑奧は百味箪笥(ひゃくみたんす)
引き出しが百ある生薬入れで、必要に応じて取り出して調合していました。忍者は薬草にも精通していて、薬を調合して怪我や病気の治療に用いたり、薬売りとして行脚したりもしていました。
甲賀流忍術屋敷には、私が見知っている以上の忍者道具のほとんど全てが展示されていました。また、受付で別料金を支払うと5回分の手裏剣を投げる事も出来ます。私も試してみましたが、的の角に辛うじて1回当てるのが精一杯でした。手裏剣の使い方はおそらく、相手の顔を目掛けて投げつけ、怯ませてから斬り付ける、または逃走するといった用い方でしょう。私はどちらかいえば、忍者の存在を疑っていましたが、忍者屋敷の凝った造りに加えて、現存する道具類の数々を見せ付けられると忍者の存在を信じざるを得ませんでした。
2023.09.02 - 城跡・史跡訪問記 其の四
山村代官屋敷は、長野県木曽郡木曽町にある代官屋敷跡である。江戸時代を通して、尾張徳川家の重臣、山村氏が代々、世襲していた。元々、山村氏「良候(よしとき)良勝父子」は、木曽氏の重臣であったが、木曽氏が改易されると一時、浪人となって逼塞した。だが、慶長5年(1600年)、関ヶ原合戦の折、徳川家康によって山村良勝が招集されると、中山道を進む東軍の先導役を務め、更に木曽郡攻略に貢献した事から、山村父子には美濃国において5700石が与えられ、更に木曽郡の支配と、福島関所の守衛も合わせて委ねられた。以降、山村氏は山村代官屋敷を拠点に木曽郡支配を担い続けた。その屋敷は大小、30棟を数える壮大なものであった。しかし、明治維新を迎えると、山村氏による支配も終わりを迎え、明治3年(1870年)、屋敷の大部分は取り壊された。現在の屋敷は、往時の三分の一程度で、下屋敷のごく一部である。






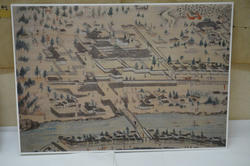






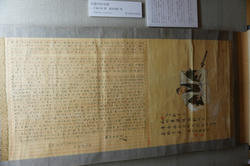
山村代官屋敷では、史料の撮影は自由との事でした。代官屋敷とは言え、広大な敷地と豪華な所持品の数々から、山村氏が相当な格式と財力を有していた事が伝わって来ます。
2023.06.18 - 城跡・史跡訪問記 其の四
犬山城は2012年8月に訪問していますが、その時は外観のみで天守閣は拝見しませんでした。今回は天守閣とその眺めを中心に写真を載せていきます。
過去の犬山城訪問記


















犬山城天守閣からの眺めは非常に良かったです。木曽川の畔にあって河川の流通を握り、旧尾張国と美濃国の両国に睨みを利かす立地だというのが視覚から伝わって来ます。
2023.05.20 - 城跡・史跡訪問記 其の四
八王子城は、東京都八王子市にある山城である。戦国関東の覇者、北条氏が築いた城で、その規模は関東屈指である。しかし、天下人、豊臣秀吉によって攻め落とされ、無数の死者を出した悲劇の城でもある。
八王子城は、天正6年(1578年)~天正10年(1582年)頃、北条家四代目当主、氏政の次弟、氏照によって築かれたと見られる。氏照は、北条家中では氏政、氏直父子に次ぐ格式と権力を誇る実力者であった。標高460mの城山には本丸と無数の曲輪が巡らされ、麓には氏照の住まう壮大な居館があり、その外には城下町が広がっていた。氏照は八王子城の更なる発展強化を構想していたが、天正18年(1590年)3月から始まった豊臣秀吉による小田原攻めによって、中断を余儀なくされる。この時、氏照は配下の数千人の兵を率いて小田原城に籠城したため、八王子城を守るのは氏照の重臣と僅かな侍衆に、招集した領民合わせて3千人余に過ぎなかった。
豊臣方の攻勢は凄まじく、北条方の支城は次々に落城してゆき、終には八王子城も、前田利家、上杉景勝、真田昌幸ら1万5千人に囲まれた。天正18年(1590年)6月23日深夜の早朝、豊臣軍は闇と霧に紛れて接近すると、城下町を一気に打ち破り、続いて山上の要害と、麓の居館を攻め立てた。豊臣軍は山上の要害は攻めあぐねたものの、麓の居館は打ち破って乱入した。そこに居た婦女子らは悲観して、御主殿の滝にて自刃していった。城方の領民達は持ち場から逃げ散っていったが、侍衆は最後まで戦わんとした。城方は中腹で必死に持ち堪えていたが、豊臣軍は数に物を言わせて背後からも攻め立てて、山頂部を乗っ取った。そして、上下から攻め立てられた城方は各曲輪で孤軍奮闘の末に全滅していった。落城は夜明け後の早朝であったようだ。
戦後、相即寺の賛誉牛秀(さんよぎゅうしゅう)上人は、死者を供養すべく城内を巡ったところ、豊臣軍、北条軍の遺体合わせて1283体を見つけたと云う。実際にはこれ以上の死者と、数倍の負傷者がいた事だろう。豊臣軍は、城内で捕らえた婦女子らを小田原城まで連行して北条方に見せつけ、また、討ち取った侍衆の首を晒したとも、城内に届けたとも云われる。小田原城の諸氏は意気消沈し、降伏開城したのはそれから間もなくの7月5日の事であった。関東には、北条家に代わって徳川家康が入ったが、八王子城は使われる事なく廃城となった。

↑八王子城遠景

↑登山口

↑金子丸
金子三郎左衛門が守っていたと伝わります。

↑柵門跡

↑城の斜面
急峻さが伝わって来ます。

↑高丸

↑展望台から東南を望む

↑本丸跡
八王子神社が鎮座しています。往時には横地監物吉信が守っていたと伝わります。

↑本丸跡
この石碑は、八王子神社の更に上にあります。

↑本丸付近の石垣

↑大手門跡
八王子城の麓にあります。この先を進むと城主の居館、御主殿に至ります。

↑大手門跡

↑曳橋(ひきはし)
往時には簡単な木橋が架けられていて、御主殿への通路となっていました。緊急時には木橋を壊し、侵入を妨げました。

↑御主殿の石垣
八王子城主、北条氏照の権威を知らしめるかの様な、見事な石垣です。

↑主殿
北条氏照はここで政務を執ったり、使者と引見したりしていたのでしょう。食事と起居は、別の建物であったかもしれません。

↑庭園

↑会所
庭園を眺めつつ、宴が催された場所だと考えられています。

↑八王子城ガイダンス施設
バス停や駐車場もあります。この施設では、映像やパネルで八王子城の歴史の説明が見れます。また、出土品の数々も展示されています。

↑八王子城の模型

↑出土品の数々
青磁碗、天目碗、風炉、香炉、炭化米などが展示されています。

↑ベネチア産のレースガラス器
戦国時代の城からは、八王子城でしか見つかっていないとの事です。

↑土玉と鉄砲弾
土玉は突起を付けて、まきびしとして使用されたと考えられています。

↑中国産の青磁皿

↑在地産の皿と壺の欠片
八王子城は巨大で、限られた時間で全てを見て回る事は出来ませんでした。けれども、城の規模と豪華な出土品の数々から、北条氏照の権力と財力の程は十分伝わって来ます。これは大大名級の城であって、5~6千人の籠城は可能であったと思われます。もし小田原攻めの際、北条氏照が配下の精鋭共々、籠城していれば、そう簡単には落城しなかったでしょう。
