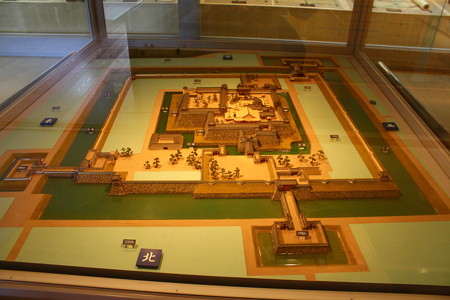プロフィール
重家
HN:
重家
性別:
男性
趣味:
史跡巡り・城巡り・ゲーム
自己紹介:
歴史好きの男です。
このブログでは主に戦国時代・第二次大戦に関しての記事を書き綴っています。
このブログでは主に戦国時代・第二次大戦に関しての記事を書き綴っています。
最新記事
カテゴリー
カウンター
アクセス解析
GoogieAdSense