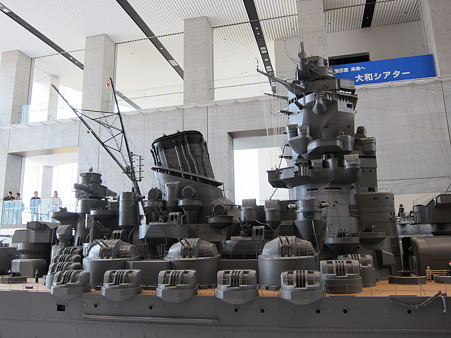18世紀、ヨーロッパの海洋帝国イギリスは、世界中から富を収奪し、それをもって世界初の産業革命を成し遂げた。イギリスの科学、工業水準は世界の最先端を走り、帝国は更に発展、拡大しつつあった。しかし、その一方でイギリスの医療水準は科学の進歩から取り残されて、人々は老いも若きも病に苦しんでいた。医療は中世からほとんど進歩しておらず、古代ギリシャの医師ヒポクラテスの教義、「全ての病気は体液の不均衡から生じる」を教義として、それを踏襲するのみだった。そして、人々は病気になれば、あらやる誤った治療法を取り入れた。カニの眼球や木屑に群れるシラミを有効な薬と信じて飲む、水銀などの有毒物資を薬として飲む、胃腸を洗浄すれば治ると信じて下剤や嘔吐剤を飲む、静脈を切開して血を抜く瀉血(しゃけつ)を行う、などなどの治療を行っては、かえって寿命を縮めるのだった。医療事故も日常茶飯事で、医者にかかれば、かえって天に召される時間が短縮される感さえあった。
18世紀半ばのイングランドの平均寿命は37歳で、とりわけ子供の死亡率は高かった。1750年から1769年の間に生まれた赤ん坊の内、半分は2歳を迎えるまでに死亡している。子供が生き延びるには体の丈夫さと、運の良さが要求された。この死と隣り合わせの年少期を切り抜けると、体に免疫が付くので、その後は比較的、長く生きる事が出来た。しかし、それでも病気の材料には事欠けなかった。当時のロンドンの居住環境は不浄そのもので、排水溝には人間の排泄物や動物の死骸が流れており、一度、水が溢れれば、それらは路上を覆い尽くした。建物からは住民の排泄物が投げ捨てられ、馬車はそのしぶきを歩行者に浴びせかける。この様な環境であるから定期的に悪性の伝染病が発生し、多くの人々が命を落としていった。勿論、抗生物質のような便利なものもないので、感染症に罹ればひとたまりも無かった。また、当時のロンドンは性風俗が盛んで、聖職者、貴族、軍人、一般市民などあらゆる階層の人々が梅毒、淋病などの性病を抱えていた。人々は絶えず病に脅かされており、生きるというのはサーカスの綱渡りの様なものであった。
内臓疾患は、不治の病に等しかった。患者が激しい腹痛を訴えても、18世紀にレントゲン撮影は存在しないので、内科医は病根を突き止められなかった。内科医も外科医も内臓疾患には基本的に無力で、病人に対して嘔吐剤や下剤を飲ませるか、瀉血を施すのみだった。瀉血はあらゆる病気に対して広く行われたが、これは何の意味も無いばかりか、瀉血のし過ぎで免疫機能が低下し、かえって病気が悪化する事も多かった。外目にもそれと分かる腫瘍や、外傷に対しては外科手術も行われたが、当時は麻酔も消毒も存在せず、道具も大昔からほとんど変わらない両刃刀とノコギリが使われるなど野蛮そのものだった。麻酔が使用されるようになるのは19世紀中頃で、消毒が確立されるのも19世紀後半である。そのため、外科手術を受ける患者は、手足を縛られて激痛に耐えねばならない。消毒の概念も無いので、傷口から細菌が侵入して重い感染症に罹る事も多かった。手術は一か八かの賭けに等しい。
戦場は、最も感染症に罹りやすい環境だった。野戦病院に銃弾がめり込んだ負傷者が運ばれてくると、軍医は拡張術と呼ばれる手術を施し、傷口を開いて銃弾をピンセットか指で摘み出し、散らばっている骨片や弾片を取り除いて、最後に傷口を縫合する。しかし、この手術を受けられるのは主に手足を負傷した者で、腹部に重傷を負った者にはお手上げで、患者は死を待つのみであった。だが、適切と思われる、この銃弾摘出手術を受けると、かえって死ぬ者が多く出た。弾丸を体内に残すと患者に痛みを残すし、そこから感染症が広がる恐れもあるので、それを摘出するという考え自体は間違っていない。だが、麻酔無しで裂けた傷口を更に広げる手術は、患者に激痛と大量出血をもたらして弱らせ、その上、軍医は消毒無しの汚れた手術器具や手で傷口をまさぐるので、感染症の機会を大幅に増やしてしまうのだった。傷の状態にもよるが、そのまま放置して自然治癒力に委ねた方が、治りが早い事例も報告されている。また、戦地は兵士の汚物で溢れ、水も汚れているので、赤痢やチフスなどの集団感染症もよく発生する。戦地では、どちらか言えば銃弾で死ぬよりも、病気で死ぬ者の方が多かった。
虫歯もイギリス人の悩みの種であった。ヨーロッパ社会で広く紅茶が飲まれるようになると、それに合わせて砂糖も大量に消費されるようになる。虫歯は老若男女を問わず、上流階級から下層階級まで平等に襲い掛かった。美しく着飾った貴婦人が微笑みかけても、その歯はがたがたで、黒ずんで欠けているなど日常茶飯事だった。当時は虫歯に対しても効果的な治療法が無いので、悪化すれば抜歯する他なかった。その抜歯であるが、何故か地位の低い者がする仕事との風潮があったので、床屋や、行商人、鍛冶屋などが主に行っていた。しかし、彼らの技量や方法はまちまちで、患者の中には歯肉をごっそりえぐられて顔が腫れあがり、一日中、激痛に苦しむ事もままあった。18世紀には、貧しい者から健康な歯を買い上げて、その歯を上流社会の者に移植する手術も流行っている。しかし、この移植された歯は、血管と神経まで縫合されていないので生着はせず、数年も経てば抜け落ちた。しかも、この移植で梅毒を移される例もあった。
18世紀のイギリスでは、「全ての病気は体液の不均衡から生じる」という古典的な教義に拘る医療従事者は今だ多かったが、それでも新進気鋭の医者の中には、患者の生前の病態と、その死後の体の状態を調べて死因を特定するという実践的、科学的な手法を取り入れる者も現れ始める。そして、人体に対する研究熱が高まって、死体解剖が広く行われるようになった。だが、その熱意に反して、検体の数は余りにも少なかった。検体には、主に死刑囚の死体が使われたがそれでも足りず、墓場に収められたばかりの新鮮な死体が次々に盗みだされていった。解剖医達は、あらゆる病死体や幼児、妊婦を含む老若男女の死体を求めたため、やがて、死体盗掘を専門とする組織まで現れ、墓荒しが横行する事態となった。真っ先に狙われるのは浅く埋められている貧しい人々の墓で、その需要が高まった時には空っぽの墓ばかりとなった。死体を巡って盗掘団同士が暴力沙汰を起こす事もあったし、珍しい病態の死体を巡って解剖医の間で争奪戦が繰り広げられる事もあった。
政府は腕の良い外科医が不足している現状を認識していたため、こういった死体泥棒や解剖医の存在を大目に見ていた。しかし、死体目的の殺人が起こるなど、死体盗掘が大きな社会問題となってくると、1832年には解剖令が施行されて、この悪習にも終止符が打たれた。医師達は、人々の目の前で犬や羊など生きた動物の腹を割いて実験して見せたり、人体実験を兼ねた危険な新治療を数限りなく行って失敗と成功を重ねていった。いくら医療の発展のためとは言え、彼らの行為は社会の規範や道徳を逸脱する面があって、数多くの批判を受けた。だが、こうした新進気鋭の医師達のあくなき探究心の結果、今まで説明のつかなかった病気の因果関係が明らかとなり、将来の予防や治療に光を当てる形となった事も確かである。そして、19世紀に入ると、観察と実験、証拠を突き詰めて病気を明らかにするという科学的手法が一般的となり、医学は飛躍的な進歩を遂げる事になるのである。
主要参考文献 「解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯」